1927年に設立された岩崎学園。これまでIT、ファッション、デザイン、リハビリテーション医療、スポーツ、医療事務、看護、保育の専門学校教育を中心に、情報セキュリティの人材育成を担う大学院大学、NPO支援や博物館など地域振興事業や、再就職支援、子育て支援事業を展開してきました。輩出した人材はのべ15万人以上を数えます。IT領域では、1983年に神奈川県下初の情報系専門学校を開校。IT教育にも注力するなか、今回のAWSに関するトレーニングが取り入れられました。
導入ポイント
- 単なる知識学習だけでなく、実践的な課題も含まれていた
- 実際に試験に合格した講師が、その勘所を教えてくれる
- 「知識学習」「問題対策」「実践」という3つの要素がバランスよく組み込まれたカリキュラムで、効率的に実力を積み上げられた
事業概要、導入の背景ならびに狙い
-
貴校のIT教育への取り組みについて教えてください。
 滋野様:情報科学専門学校では、システム開発、AI、IoT、VR、eスポーツ開発、セキュリティ、Webデザイン、ネットワークなど多様なIT分野に応じた学科を持ち、それぞれの分野での就業を目指した教育サービスを提供しています。実習形式での授業を主体とし、学んだスキルを実践的に身に付けることができるIT教育が特徴です。
滋野様:情報科学専門学校では、システム開発、AI、IoT、VR、eスポーツ開発、セキュリティ、Webデザイン、ネットワークなど多様なIT分野に応じた学科を持ち、それぞれの分野での就業を目指した教育サービスを提供しています。実習形式での授業を主体とし、学んだスキルを実践的に身に付けることができるIT教育が特徴です。
こうして身に付けたスキルを社会で実践する取り組みも行っており、近年の例ですと、文部科学省が掲げている教育指針「GIGAスクール構想」の支援として、学生が中学校でのICT環境構築の支援を行い、ITスキルを活かして教育現場をサポートする取り組みを行っています。- また、学生の習熟度や目標に応じてクラス分けを行っており、面倒見の良い教育を提供しています。
そもそもAWSを選んだ理由ですが、実はAWS環境下での学習自体は導入していました。というのも、AWSはクラウドのトップシェアを誇りますし、実績も数多くあります。社会に出て活躍していけるエンジニア育成のためには、AWS学習が必須だと考えています。そこで資格取得や、実践的な内容も得られると思い、今回スカイアーチネットワークスのAWS認定取得支援プログラム導入に至りました。
学びの効果
-
今回、講座を受講した理由について教えてください。
 本谷様:もともと私は開発職を目指しており、インフラのことも知っておいたほうが差別化に繋がると考えて、AWSに興味を持ちました。中学生くらいのときにゲームにハマったのがきっかけだったのですが、自分でゲームを作りたいと思い、本を買って、開発をするようになっていったんです。その後、自分の作るもので人の生活を便利にしたいと考えて、専門学校を選びました。
本谷様:もともと私は開発職を目指しており、インフラのことも知っておいたほうが差別化に繋がると考えて、AWSに興味を持ちました。中学生くらいのときにゲームにハマったのがきっかけだったのですが、自分でゲームを作りたいと思い、本を買って、開発をするようになっていったんです。その後、自分の作るもので人の生活を便利にしたいと考えて、専門学校を選びました。
そんな中、昨年別の授業でAWSに触れる機会があり、クラウドの可能性に興味を持ちました。もっとAWSの全体像を理解したいと考えていたところ、今回のAWS認定取得支援プログラムの話を聞き、すぐに受講を決めました。
-
全体の学習を通して、どんなことが学べましたか? 良かった点を教えてください。
- 本谷様:AWSの基礎知識が広く学べました。それを学ぶ過程で、自分の学習習慣を客観的に把握できたのも、一つの学びでした。実際、スカイアーチから提供のeラーニングで学習時間が可視化されていたので、毎日チェックしていたのですが、モチベーションになってよかったです。
それに、今回の講座で、AWSは本当にいろんなことができるんだなと思いました。特に、近年注目を集めているAI関連サービスがAWSにも複数あることを初めて知り、今後AWSを学んでいく中でそれらのサービスにも触れてみたいなと思いました。
-
講座で提供された学習教材はいかがでしたか?
-
本谷様:講座を受けるまで、モヤモヤしていた部分が多かったのですが、配布されたプリントなど、内容がとても分かりやすくて、モヤモヤが解消できたので、資格合格に繋がったのかと思います。
加えて、AWSのクラウドクエスト(ゲームをプレイしながらAWSを学べる学習コンテンツ)も、とてもよかったと思います。単に知識を得るだけでは定着しづらいので、クエスト形式は自分に合っていると感じました。講義でAWSのサービスの説明を受けてからクラウドクエストにチャレンジすると抵抗感なく進められました。
また、eラーニングはどこでも、手軽にアクセスできます。電車の中や、何かの待ち時間で勉強できるのはとても便利でした。
-
先生から見て、効果的だと感じた点はありましたか。
 滋野様:先ほどあったように、今回、知識学習、問題対策としてのeラーニング、実践としてのクラウドクエスト、3つのアプローチが用意されていました。このようにバランスよく3つの要素が含まれたカリキュラムは他にありません。効果的な学習環境・体系が組まれているので、これからの結果が楽しみです。
滋野様:先ほどあったように、今回、知識学習、問題対策としてのeラーニング、実践としてのクラウドクエスト、3つのアプローチが用意されていました。このようにバランスよく3つの要素が含まれたカリキュラムは他にありません。効果的な学習環境・体系が組まれているので、これからの結果が楽しみです。
また、実際に試験合格された講師の方から、試験の勘所などを教えてもらえるのは大きなプラスだったと思います。
-
今後期待されることはありますか。
-
滋野様:授業時間との兼ね合いもありますが、他の試験対策講座も検討したいですね。
本谷様:私も、今後、上の資格を目指していきますので、そちらの対策講座があれば受けてみたいです。
札幌デザイン&テクノロジー専門学校(以下、TECH.C.札幌)は、日本全国及びアメリカNYに6法人82校の教育機関を擁する滋慶学園グループの1校です。2012年、札幌放送芸術専門学校として設立されました。当初はミュージカルなどの分野のみの専門学校でしたが、社会とテクノロジーの変化とともにその領域を拡張し、2021年には4年制学科にて高度専門士取得ができるAI・ホワイトハッカー・ゲームクリエイターのコースを新設。校名を「札幌デザイン&テクノロジー専門学校」に変更し、日本の未来を担うサイバーセキュリティ人材、テクノロジー人材を育成する教育機関として、現在に至っています。
このような背景があり、TECH.C.札幌様は、実践的なクラウド教育を求めて、ホワイトハッカーコースを受講する学生を対象に、スカイアーチネットワークスのAWSトレーニングサービスを導入いただきました。札幌校ではオフライン・オンライン両方で、仙台校ではオンラインで、計38名の学生が受講しました。
本記事では、導入前の課題・AWSトレーニングに対する期待と、導入後の実際の感想、効果を2回に渡って取材した様子をお伝えします。
導入ポイント
- AWS認定クラウドプラクティショナー資格取得に向けた実践的な研修内容を提供している
- ホワイトハッカーコースの内容に、ビジネスの実務的な技術・知識を加えることで、学生の学習意欲の向上が期待できる
- AWSのプロフェッショナルから直接指導を受けることで、学生が将来の仕事をイメージしやすくなることを期待できる
事業概要
-
貴校のIT教育への取り組みについて教えてください。
- 川崎先生:本校は元々放送芸術専門学校として12年の実績がありましたが、近年のIT人材の需要増加を受けて、デザインテクノロジー専門学校へと校名変更し、IT教育に注力するようになりました。2025年の春、初めての卒業生を輩出する予定です。
この4年前から新設されたAI&テクノロジー科ですが、ホワイトハッカーやAIエンジニアなどの専攻に分かれており、いずれも実践的な教育を行っています。IT業界で活躍できる即戦力人材の輩出を目指し、講師は全員が現役のエンジニアやクリエイターです。
-
専門学校、また貴校ならではのIT教育の特徴はどのような点でしょうか。
- 川崎先生:やはり実践的な演習中心のカリキュラムが強みです。講師は現役のエンジニアやクリエイターの方ばかりで、最前線の知見を学生に直接指導していただいています。4年間じっくりIT分野の専門教育を行い、業界と連携した産学連携教育を通して創造力を身につけることで即戦力を育成できる点が、大学との大きな違いです。
導入の背景ならびに狙い
-
AWSトレーニングサービスの導入の背景を教えてください。
- 川崎先生:セキュリティ分野ではクラウドの知識が不可欠ですが、基礎的な内容にとどまっていました。セキュリティ分野でクラウドの理解は不可欠ですし、ゲーム開発でもクラウドの活用が広がっています。その中でも、AWSのユーザー企業は増加しています。そこでAWSのアカデミック向けプログラムを活用し、講師を探していたところ、スカイアーチネットワークスをご紹介いただきました。
-
当社のトレーニングサービスを通して、どのような変化を期待されていますか。
- 川崎先生:まず、現在のカリキュラムに不足しているクラウド技術とAWSについて学ぶ機会を学生に提供できますので、歓迎したいです。また、当校の講師と同様、スカイアーチネットワークスのAWSトレーニングサービスも、現役のエンジニアのサポートがあると聞いています。実践的な内容を学び、卒業後に役立つスキルを身につけてもらいたいです。
また、外部の研修サービスの採用で、当校としては、講師のバリエーション拡大も狙いの一つです。AWSのプロフェッショナルから直接指導を受けることで、学生が将来の仕事をイメージしやすくなり、将来の選択肢が広がることや、学習意欲の向上を期待しています。
AWS認定は、就職活動でも大きなアピールポイントになります。専門学校の4年間は貴重な時間です。しっかりと研修に取り組み、目の前のチャンスを最大限に活かして、スキルを磨いていってほしいと思います。
学びへの期待
-
AWSトレーニングサービスをこれから実際に受ける、ホワイトハッカー専攻所属の学生である鈴木さんにお聞きします。ホワイトハッカー専攻に所属するきっかけや、現在学んでいることを教えてください。
- 鈴木さん:私がホワイトハッカー専攻に進学するきっかけになったのはある漫画です。小学生の頃からパソコンが好きだったこともあり、ホワイトハッカー専攻に入学することを決意しました。
日々勉強をする中で、最近はサーバー系の仕事に就きたいと考えており、クラウドの勉強にも興味を持っています。
-
AWSに対する事前知識、また、これから受講するトレーニングはどのように受講したいと思われていますか。
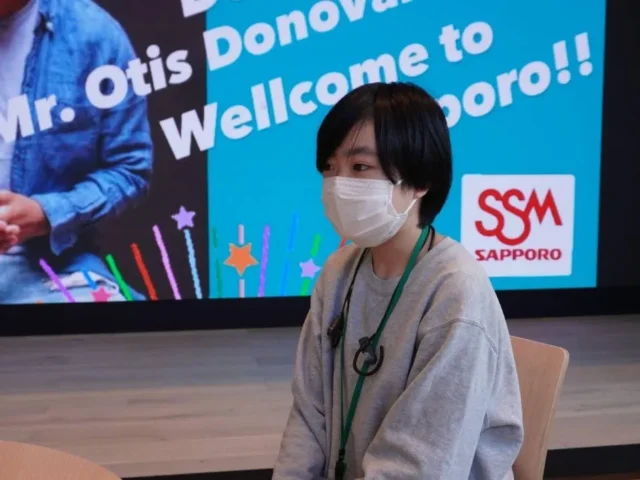 鈴木さん:先ほどお伝えした通り、クラウドの勉強をする中で、AWSにも興味を持ちました。AWSを使ったアプリ開発に挑戦したこともあります。
鈴木さん:先ほどお伝えした通り、クラウドの勉強をする中で、AWSにも興味を持ちました。AWSを使ったアプリ開発に挑戦したこともあります。
このトレーニングサービスでは、研修を受けつつ、AWS認定クラウドプラクティショナーと同等程度の知識が身につくと聞きました。クラウドプラクティショナーは、AWSの認定資格の中でも、基礎として位置付けられる資格と聞いています。そのため、この研修とクラウドプラクティショナーの認定取得を通じて、他の資格勉強にも役立つクラウドの基礎知識が身につけばと思っています。
AWSトレーニングサービスを約3カ月の講座として実施しました。以下は、講座終了後のインタビューの内容をお届けします。
-
実際に受講いただいて、どうでしたか?
- 鈴木さん:元々興味があったものの、知識がありませんでしたので、クラウドの基礎知識を知れたのは何より良かったことです。
ただ、AWSの機能について、フルネームで出てくる箇所と略称が入り混じって、最初は混乱しました。また、AWSサービスのカテゴリーを覚えるのに苦労しました。
-
当社の講座を受けてみて分かりやすかった点、工夫して欲しい点はありますか。
- 鈴木さん:動画は聞き取りやすく、スライドも見やすかったです。動画は見返せるので、当初覚えられずにつまずいた箇所も、だんだんと分かるようになりました。
一方で、進むスピードが早くてついていくのが大変でした。また、試験対策を意識した日本語にも慣れなかったです。
-
今後のAWSへの興味はどのように変化しましたか?
-

<講座開始の様子>
鈴木さん:全く知識がなかったのですが、今回の受講で知識をつけられて良かったです。特にサービスの中で、AWS Direct Connectは個人的に面白そうだなと思いました。クラウドの勉強を通して、いろいろな業界に広がっていきそうな可能性を感じました。今後は資格取得も検討しているところです。
-
先生にお聞きします。今回クラウドの中でもAWSを選んで導入された理由について教えてください。
- 川崎先生:はい。実は姉妹校でAWSとの産学連携企業プロジェクトなど、いくつかのプロジェクトがすでにあったためです。ちょうどこれから、AWS AIプロジェクトが始まるのですが、AWSの講座を受講していないと参加できません。また、世界的に導入が広がっているのもポイントの一つでした。

<対面講義の様子:最後の講義は対面で行いました>
スカイアーチネットワークス 佐藤 広国
-
講座導入で良かった点、難しかった点はありますか。
 川崎先生:動画や資料を見返せるのは良かったです。動画とスライドを見比べながら進められたのはやりやすかったと思います。学習意欲の高い学生は、講義と復習で使えて、知識を深めることができたのではないかと思います。その一方で、受講はしているもののそこまで興味関心が高くない学生は、どこまで内容を理解しているのか計りかねますし、当校はAWSのプロフェッショナルではないので、意欲をさらに向上させる工夫が足りなかったのは次への課題ですね。難易度や講義中のメリハリについては模索したいですね。
川崎先生:動画や資料を見返せるのは良かったです。動画とスライドを見比べながら進められたのはやりやすかったと思います。学習意欲の高い学生は、講義と復習で使えて、知識を深めることができたのではないかと思います。その一方で、受講はしているもののそこまで興味関心が高くない学生は、どこまで内容を理解しているのか計りかねますし、当校はAWSのプロフェッショナルではないので、意欲をさらに向上させる工夫が足りなかったのは次への課題ですね。難易度や講義中のメリハリについては模索したいですね。
-
今回の講座導入前と後で、一番の変化はなんでしょうか。
- 川崎先生:今回、学生には受講の希望有無をとらずに導入しました。そのような中、初めてAWSを知ってもらったこと、そして今後は将来を見据えた選択肢にAWSが早速加えられているのが一番ではないでしょうか。導入後、資格試験を受験してみたい学生が38名中4、5名出てきています。
-
講座を採用された今後貴校のカリキュラムにAWSの講座は活かせそうでしょうか。
- 川崎先生:そうですね。今回のような資格対策もそうですし、実際の企業の方から教わるのは、学生にとっては貴重な機会でした。これまでクラウドの講座はありませんでしたが、ホワイトハッカー専攻では、クラウドという単語自体が出てくる回数が増えていますし、実際に、社会でもクラウド活用が進んでいる現状は認識しています。姉妹校ではすでにクラウドの内容に踏み込んでいるところもあり、学生が将来社会に出たときに、基礎知識だけでも身につけておく必要があるなと考えています。
最近では生成AIも日々進化して、私たちにも身近な存在になっていますが、AI×クラウドのような掛け合わせも興味深いです。学生たちの中でも生成AIは調べ物などに活用しているようで、使い慣れてきています。クラウドも同じように基礎的な知識を持っていると将来の幅が広がりそうです。
-
今後の、学生さんへのメッセージはありますか。
 川崎先生:今はクラウドゲームの流行や、企業セキュリティもクラウド化するなど、どの領域でもクラウドを避けて通ることはできません。先ほどの鈴木さんのように、これから学生が卒業していく2年後、3年後には、もっと普及していることが予想されます。学生が卒業する際、またその後も、クラウドのプロフェッショナルでなくても、クラウドに携わること、またクラウドを学んだことをきっかけに、新しいことにチャレンジできるようになってほしいと思っています。
川崎先生:今はクラウドゲームの流行や、企業セキュリティもクラウド化するなど、どの領域でもクラウドを避けて通ることはできません。先ほどの鈴木さんのように、これから学生が卒業していく2年後、3年後には、もっと普及していることが予想されます。学生が卒業する際、またその後も、クラウドのプロフェッショナルでなくても、クラウドに携わること、またクラウドを学んだことをきっかけに、新しいことにチャレンジできるようになってほしいと思っています。
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社(以下、MDIS)は、金融業、製造業、流通・サービス業向けシステム事業を推進するリーディング・サービスインテグレーターとして、三菱電機グループの技術力やサービスを最大限に活用した各種ITサービス事業を展開しています。「三菱電機の戦略IT企業」として、2001年に分社化しました。
現在は情報システムの企画から開発、販売、運用・保守に至るまで、ワンストップでソリューションを提供しています。
MDISはスカイアーチネットワークスと2023年、クラウドに特化したソリューションの提供を目的に、クラウドセントリックを設立しています。
今回同社では、さらにクラウドシフトの動きを加速するため、バーチャルOJTの導入を行いました。
導入ポイント
- バーチャルOJTで、資格のためだけでない知識を習得できる
- 案件以外で実務経験が積める
- 実際の案件に限りなく近いプロジェクト進行を体験できる
事業概要
-
MDISの提供するサービスについて教えてください。
-
 桑原様:MDISは「三菱電機の戦略IT企業」として、2001年に分社化し、現在に至ります。特に金融、製造、流通・サービス業の領域に強みを持っています。現在はそうした領域のお客様でもオンプレではなく、クラウドシフトが進んでいます。ビジネススピードの変化によって当社でもお客様のニーズに応えるため、クラウドシフトを今まさに加速させているところです。
桑原様:MDISは「三菱電機の戦略IT企業」として、2001年に分社化し、現在に至ります。特に金融、製造、流通・サービス業の領域に強みを持っています。現在はそうした領域のお客様でもオンプレではなく、クラウドシフトが進んでいます。ビジネススピードの変化によって当社でもお客様のニーズに応えるため、クラウドシフトを今まさに加速させているところです。スカイアーチネットワークスと共同で、クラウドセントリック株式会社を設立したのもその流れがあってこそです。クラウド関連事業やプロジェクトへの対応力強化に資する専門技術者集団として、クラウドインテグレーション事業の拡大の先陣を切る会社です。
クラウドセントリック独自で採用を行い、クラウドソリューションを提供するだけでなく、MDISにそのノウハウを展開することで、三菱電機の目指す「循環型 デジタル・エンジニアリング企業」への変革に貢献することも期待されています。
-
MDISがクラウドの研修を導入した理由を教えてください。
- 桑原様:前述の通り、お客様のニーズに応えるべく多くのクラウド関連プロフェッショナル人材を育成しています。具体的な施策の一つとして、AWSの資格取得支援を始めています。2023年9月現在、610名が資格取得済みです。今後も資格取得支援は継続していきますが、今回は資格取得後のステップとして、実務経験を積むためにスカイアーチネットワークスのAWSトレーニングのプログラムの一環である、バーチャルOJTを採用しました。プロジェクト以外でも実務経験を積むことで、先取りして経験とノウハウを蓄積していきたいのが狙いです。
導入経緯、導入前の課題
-
様々な研修サービスがあるなかで、バーチャルOJTを導入した経緯について教えてください。
 桑原様:実務経験を積む場が不足していたことに、経営陣含めて課題感を持っていたのが理由です。資格を取得した610名はSEのみならず、営業も含んでいます。基礎的な位置付けの資格だけでなく、応用の位置付けである資格取得者もいますが、学んだ知識をどのようにアウトプットするのかが重要です。そのためにお客様への提案業務から設計・構築までをワンストップで体験できるバーチャルOJTを選びました。
桑原様:実務経験を積む場が不足していたことに、経営陣含めて課題感を持っていたのが理由です。資格を取得した610名はSEのみならず、営業も含んでいます。基礎的な位置付けの資格だけでなく、応用の位置付けである資格取得者もいますが、学んだ知識をどのようにアウトプットするのかが重要です。そのためにお客様への提案業務から設計・構築までをワンストップで体験できるバーチャルOJTを選びました。
バーチャルOJTについて
-
研修を受講しようと思ったきっかけや、研修を受ける前はどのような気持ちをお持ちでしたか。皆さんはどれくらいの前提知識をお持ちだったのでしょうか。
-
 岡本様:私は入社2年目から現在の部署に異動になりました。異動後はクラウド関連業務に携わり、Professionalレベルの資格を取得しましたが、お客様に提案する機会があまりありませんでした。バーチャルOJTでは提案も経験できるということで、参加しました。また、プロジェクト全体の工程と工程ごとに必要になるドキュメントも把握できることも期待していた一つでした。
岡本様:私は入社2年目から現在の部署に異動になりました。異動後はクラウド関連業務に携わり、Professionalレベルの資格を取得しましたが、お客様に提案する機会があまりありませんでした。バーチャルOJTでは提案も経験できるということで、参加しました。また、プロジェクト全体の工程と工程ごとに必要になるドキュメントも把握できることも期待していた一つでした。乃美様:私は以前からクラウドに関心があったため、独自に勉強を進め、資格取得もしていました。現在はAssociateレベルの資格まで取得しています。今回は実務経験を積みたいと思い参加しました。
桑原様:乃美さんは個人としても会社としても、クラウド領域を伸ばしていきたい思いを持っていた方だったので、参加してもらいました。
 上村様:私が所属している課では、Professionalレベルの資格まで取得している人も多く、AWS関連の案件を、多く対応しています。以前私も同じプロジェクトに参加したことがあるのですが、その人に頼りっきりになってしまっていました。それがきっかけで、今度は一緒に推進していけるようになりたいと思い、今回の研修に参加しました。
上村様:私が所属している課では、Professionalレベルの資格まで取得している人も多く、AWS関連の案件を、多く対応しています。以前私も同じプロジェクトに参加したことがあるのですが、その人に頼りっきりになってしまっていました。それがきっかけで、今度は一緒に推進していけるようになりたいと思い、今回の研修に参加しました。
-
実際に研修を受けてみてどうでしたか。
-
 乃美様:普段業務で行っている案件の推進とはあまりギャップがなく、これまでの経験が役に立った印象があります。大きな違いを感じたのは、AWSの設計や構築の仕方です。実務経験がないと辛いなと感じました。
乃美様:普段業務で行っている案件の推進とはあまりギャップがなく、これまでの経験が役に立った印象があります。大きな違いを感じたのは、AWSの設計や構築の仕方です。実務経験がないと辛いなと感じました。私は先ほどAWSの資格を取得しているとお伝えしましたが、サービスに対する知識が浅かったので、バーチャルOJT時には調べながらの対応になりました。資格取得だけの知識だけでは足りないなと実感しました。
岡本様:受講する前は、設計というよりもコンソールなどを触って、開発をどんどん進めていくんだろうなというイメージがありました。ですが、実際にやってみるとお客様役とのコミュニケーションや設計書などのドキュメント作成も行いました。プロジェクトの中で使ったデータベースサービスの知識がより深まったのと、コミュニケーションや説明スキルも向上しているように思います。他の案件と一緒で、設計のフェーズはすごく大事なんだなと、良い気づきになりました。
上村様:特に印象に残っているのは、お客様役のニーズに応える際、プランをいくつか立てられても、どちらがいいのか迷った場面があったことです。実際にやってみないと分からないつまずきポイントがあることが、バーチャルOJTで分かりました。
-
研修中、工夫した点はありますか?
- 岡本様:バーチャルOJTは実際の案件と同様、チームで進めていく必要があります。そのため、チーム内のコミュニケーションを意識して取り組みました。進捗管理や作業で発生した問題について、それを1人で抱え込まずに、チーム全体で共有し、フォローし合いながら進めました。
上村様:他の人が指摘されたことも自分のこととして捉え、学ぶようにしていました。
-
今後実際の業務で活かしていきたい点、今後の目標があれば教えてください。
-
上村様:私は今年課に配属された新人の育成担当になりました。バーチャルOJT内で、どう分かりやすく伝えるかは、かなり考えて取り組みましたので、研修で学んだコミュニケーションを生かしながら教えていきたいと思います。「教える」というアウトプットができるので、学んだことが定着するのではと期待しています。
 岡本様:私はProfessionalレベルまでの資格を取得していますが、バーチャルOJTを通して、もっと知識をつけたいと思うようになりました。多くの知識を身につけて、実際の商談対応に生かしていきたいです。
岡本様:私はProfessionalレベルまでの資格を取得していますが、バーチャルOJTを通して、もっと知識をつけたいと思うようになりました。多くの知識を身につけて、実際の商談対応に生かしていきたいです。乃美様:私もProfessionalを目指して勉強を続けるのと、AWS以外のクラウドにも興味があるので、幅を広げたいと思っています。今後クラウドプロジェクトに参加する際は、早期立ち上げに貢献できるようにと、考えています。
今後の人材育成計画、スカイアーチネットワークスへの期待について
-
実際に研修を受講したメンバーからの感想がありましたが、受講者に対する今後の期待はありますか?
- 桑原様:今後の期待は大きく2つあります。まずは周りの人にスキルトランスファーをしていってほしいということです。すでに上村さんが新人育成にあたっていますが、周囲の人を巻き込んで、クラウドシフトを推進する役目を担ってほしいと思います。また、今回の研修の学びを自分で振り返り、今後も知識を増やす、資格を取得するといった勉強を継続していってほしいと思います。

リアルソフトは、ERP導入支援を中心に、企業向け業務システムの開発を行っています。創業当初からオンプレミスのシステム構築が主流でしたが、最近ではSaaSのシステム構築が求められています。そこでスカイアーチネットワークスのAWS認定取得支援プログラムが採用されました。リアルソフトでは開発メンバーだけでなく、社内の研修担当も受講。本記事では導入前の課題や実際に受講した感想、学びを伺っていきます。
受講コース
- AWS 認定取得支援プログラム
- クラウドプラクティショナー(CLF)
- ソリューションアーキテクト アソシエイト(SAA)
- AWS公式トレーニング
- AWS Technical Essentials(TESS)
- Architecting on AWS(AonA)
導入ポイント
- AWSの認定資格に強い
- 知識だけでなく、経験が積める
- 知識と経験の体系だったカリキュラムが組まれている
事業概要
-
リアルソフトの提供するサービスについて教えてください。
 板崎 様:リアルソフトはERP導入支援を、設立まもない時期から行っています。ERP事業部のほか、SI事業部があり、今は全体で50名ほどのエンジニアが働いています。
板崎 様:リアルソフトはERP導入支援を、設立まもない時期から行っています。ERP事業部のほか、SI事業部があり、今は全体で50名ほどのエンジニアが働いています。
-
クラウドの研修を採用いただきましたが、御社でクラウドが必要になった背景について教えてください。
- 板崎 様:私たちはInfor Japan社のサービスパートナーとして、組立製造業向けERPシステムであるSyteLineの導入支援をしていますが、こちらはオンプレのシステムでした。しかし最近になってSaaS版が登場しました。オンプレの時は、必要があれば同じサーバー内に追加で開発をすればよかったのですが、SaaSとなるとそうはいきません。必要に応じてAWSをベースに、サーバーも別で用意しながら開発をすることもあります。そうした開発の理解を深めるため、今回スカイアーチネットワークスのサービスを導入するに至りました。
導入経緯、導入前の課題
-
今回AWS認定取得支援プログラムを導入された経緯について教えてください。
-
 板崎 様:他にもいろいろとサービスは検討していたのですが、5名まとめて受講するコースがあったのと、スカイアーチネットワークスの強みが活かされていることに期待しました。我々はどちらかというとアプリケーションの開発に強みがあります。インフラに対しても今回を機に知識と経験を強化したいと考えました。
板崎 様:他にもいろいろとサービスは検討していたのですが、5名まとめて受講するコースがあったのと、スカイアーチネットワークスの強みが活かされていることに期待しました。我々はどちらかというとアプリケーションの開発に強みがあります。インフラに対しても今回を機に知識と経験を強化したいと考えました。また、先般、AWS環境の構築を含めた、大きな案件があったこともきっかけの一つです。我々だけではまかないきれず、スカイアーチネットワークスと一緒に提案をしましたが、結果機会を逃しました。今後こうした提案があった際に、より受注確度を高めたいですよね。受注したあとも、一定の知識があればプロジェクトもスムーズになります。スカイアーチネットワークスの研修は業務にフォーカスして経験を積めるので、学んだことがすぐに役立つだろうという期待がありました。
 出口様:スカイアーチネットワークスの研修を受講する前に、教育チームとして対策は進めていました。月に4時間、業務時間内に動画視聴で学習できる制度を展開しています。しかし、AWSに特化した教育までは手が回っていませんでした。
出口様:スカイアーチネットワークスの研修を受講する前に、教育チームとして対策は進めていました。月に4時間、業務時間内に動画視聴で学習できる制度を展開しています。しかし、AWSに特化した教育までは手が回っていませんでした。
AWS認定取得支援プログラムについて
-
AWS認定取得支援プログラムは今回、5日間で実施いただきました。月4時間の学習時間を目標とされていましたが、時間の調整はどのようにされたのでしょうか。
- 出口様:今回参加した5名のうち、3名がお客様のいるプロジェクトに所属、2名は社内の研修担当でした。研修担当は、新人研修の演習時間を多めに増やすなどして対応し、お客様のいるプロジェクトの場合は前後の残業などで対応しました。
-
普段の業務と調整しながら、かつAWS認定取得支援プログラム中は課題があれば自分で調べて進めることも必要です。モチベーションはどのように保っていましたか。
 出口様:私は過去AWS構築込みの案件を、独学の知識で提案したことがありました。その際、他に最適解があったのではないだろうかと、自分の中でモヤモヤした思いがあり、AWS認定取得支援プログラムで体系的に学べるのではと期待していました。
出口様:私は過去AWS構築込みの案件を、独学の知識で提案したことがありました。その際、他に最適解があったのではないだろうかと、自分の中でモヤモヤした思いがあり、AWS認定取得支援プログラムで体系的に学べるのではと期待していました。
他のメンバーの中には資格のロゴが名刺に増えるのが嬉しいと言っている人もいましたよ!(笑) みんなそれぞれのモチベーションがあったと思います。
-
難易度はどうでしたか?
- 出口 様:基礎的な内容は経験があるので問題なかったと思いますが、資格試験対応に苦戦した人もいたようです。また、自分で考える部分について、意図を汲みながら進めるのはやや難しかったです。
-
実際に研修を受けてみてどうでしたか。
- 出口 様:受講後、「AWSに関するお客様からの問い合わせにどう答えたらいいか。」という相談を受けた際、こういうケースならこうしたほうがいいのではないかと、受講メンバーで話し合って回答できたのはよかったです。研修を受けていないとなかった風景だったと思います。
-
今後実際の業務で活かしていきたい点を教えてください。
- 出口 様:まだ実際に業務があるわけではありませんが、今後先ほどのような相談が増えたり、業務でアサインされたりすることはあると思います。
今後の人材育成計画、スカイアーチネットワークスへの期待について
-
研修を受けてみて、今後の活用方法や、当社への期待があれば教えてください。
 出口 様:私は研修担当もしています。現状は、リアルソフトの社員が学ばなければならないことのサポートができていると思います。しかし、実際にスカイアーチネットワークスの研修を受けてみて、それぞれの学びたいことを学べる環境作りが必要だと感じました。社内で他のメンバーにも受けてほしいと思います。
出口 様:私は研修担当もしています。現状は、リアルソフトの社員が学ばなければならないことのサポートができていると思います。しかし、実際にスカイアーチネットワークスの研修を受けてみて、それぞれの学びたいことを学べる環境作りが必要だと感じました。社内で他のメンバーにも受けてほしいと思います。
TOPPANエッジは、「情報」を核として「インフォメーションソリューション事業」「ハイブリッドBPO事業」「コミュニケーションメディア事業」「セキュアプロダクト事業」の4つの領域で事業活動を展開しています。
今回お話を伺ったデジタルソリューション本部では従来のオンプレミスシステムを使った業務から、クラウドの導入や、クラウドを活用した業務プロセスのシフトが進んでいました。とはいえ主要なクライアントは金融機関。高いセキュリティ、システム要件は高いクラウドの企画力、設計力も求められ、専門性の高い人材育成、確保が課題でした。
そこで同社ではこれまで社員を対象に、1000人規模のクラウド教育プロジェクトを実施。次のステップとして、実際に社内の業務やクライアントのプロジェクトへの活用と経験の蓄積、そのための実践の場が必要でした。そこでスカイアーチネットワークスのバーチャルOJTが採用されました。本記事では導入前の課題や実際に受講した感想、学びを伺っていきます。
導入ポイント
- バーチャルOJTで実務そのままのプロジェクトを体験できる
- 開発者として経験を積みたい人、マネジメントを学びたい人が一つのチームで双方にとって学びのある研修内容
- AWSに精通しているエンジニアのサポートがあり、実務でどのように対応しているかも含め回答をもらいながら進められる
事業概要
-
TOPPANエッジの提供するサービスについて教えてください。
 田坂:TOPPANエッジはビジネスフォームやデータ・プリント・サービスなどの分野で培ってきた技術やノウハウをベースに、お客様の情報伝達を最適化する情報管理ソリューションを提供しています。印刷物と電子ドキュメントの融合や、RFID・ICなどの情報メディア、プリンテッド・エレクトロニクス技術を応用した製品開発など、「情報」を核としたさまざまな事業を展開しています。
田坂:TOPPANエッジはビジネスフォームやデータ・プリント・サービスなどの分野で培ってきた技術やノウハウをベースに、お客様の情報伝達を最適化する情報管理ソリューションを提供しています。印刷物と電子ドキュメントの融合や、RFID・ICなどの情報メディア、プリンテッド・エレクトロニクス技術を応用した製品開発など、「情報」を核としたさまざまな事業を展開しています。
-
クラウドの研修を採用いただきましたが、御社でクラウドが必要になった背景について教えてください。
- 田坂:前述したソリューションは数年前までオンプレ中心に、開発・提供をしていました。しかし世の中のトレンドの変化、スピード感の加速を感じ、それを実現するクラウドへのシフトを検討していました。
しかし私たちの顧客の中心は金融業界の皆さんです。セキュリティなどの観点から、クラウド自体が許容されない時期もありました。それでも変化の波がやってきたのは、コロナ禍のタイミングでした。デジタル化が進んだ印象がありますね。今では金融業界のお客様にとって、スピードの優先順位が相対的に上がったように思います。実際にクラウドを選択することも増えています。
そのような背景から、当社では数年前から資格取得の支援を行ってきました。2024年度に向けて100名の資格取得者輩出の目標は、延べ人数では現時点ですでに達成されています。そうなると次の課題は、実践の場に向けた準備です。お客様の要求レベルが高い案件でも、お客様と折衝ができるようにならなければいけません。そのためできるだけ実践に近い、経験値が積める研修や対策ができないか、選択肢を模索していました。
導入経緯、導入前の課題
-
今回バーチャルOJTを導入された経緯について教えてください。
-
 大串:私は資格取得や研修の推進を担当しており、田坂が申し上げた資格取得も積極的にサポートしてきました。ただ、知識の習得も大事ですが、実際の業務を考えるとその知識の使いこなしが必要になります。そのための研修を探してはいましたが、なかなか実践的な研修は探すことができませんでした。そんな中、スカイアーチネットワークスのAWSトレーニングのプログラムの一環である、バーチャルOJTが目にとまりました。
大串:私は資格取得や研修の推進を担当しており、田坂が申し上げた資格取得も積極的にサポートしてきました。ただ、知識の習得も大事ですが、実際の業務を考えるとその知識の使いこなしが必要になります。そのための研修を探してはいましたが、なかなか実践的な研修は探すことができませんでした。そんな中、スカイアーチネットワークスのAWSトレーニングのプログラムの一環である、バーチャルOJTが目にとまりました。 右田:私たちのチームはお客様の要件をヒアリングし、SaaSサービスなども含め、要件を満たすシステム全体を企画・設計・提案するチームです。特にお客様のシステム部へのヒアリング、提案をする際、深い業務理解やシステム理解があると、信頼を得て、結果的に受注確度が上がります。お客様は大手の金融機関の方が多く、プロのSEとして専門知識が求められます。その際に経験談を含めた話ができると非常に話が進みやすくなります。そうした経験をプロジェクト以外で積めるのはチームとしてもとても助かります。そのため、中には1日フルでの研修日もありましたが、チームで普段の業務量を調整してスカイアーチネットワークスの研修に参加してもらいました。
右田:私たちのチームはお客様の要件をヒアリングし、SaaSサービスなども含め、要件を満たすシステム全体を企画・設計・提案するチームです。特にお客様のシステム部へのヒアリング、提案をする際、深い業務理解やシステム理解があると、信頼を得て、結果的に受注確度が上がります。お客様は大手の金融機関の方が多く、プロのSEとして専門知識が求められます。その際に経験談を含めた話ができると非常に話が進みやすくなります。そうした経験をプロジェクト以外で積めるのはチームとしてもとても助かります。そのため、中には1日フルでの研修日もありましたが、チームで普段の業務量を調整してスカイアーチネットワークスの研修に参加してもらいました。
-
研修を受講しようと思ったきっかけや、研修を受ける前はどのような気持ちをお持ちでしたか。皆さんはどれくらいの前提知識をお持ちだったのでしょうか。
-
五十嵐:私はオンプレの開発部門に所属しており、あまりクラウドを使っている部署ではありませんでした。しかし昨年からクラウドの案件が徐々に始まり、関心を持っていました。とはいえ私個人は業務では全くクラウドには触れていなかったので最初は不安でした。
黒馬:私はSEとして、ローコードで開発を行っております。しかし、構築後のアプリケーションの運用・監視などの経験はありませんでした。クラウドについては何となく知識を持っている程度でした。
 後藤さん(左から2番目):私は前職でAWSではない、別のクラウドを触っていて、クラウド自体には慣れていました。4月の中途入社前からこの研修を受講することは決まっていて、AWSは初めてでした。AWSの知識を身につけるとともに、マネジメントもやってみたいと考えていました。
後藤さん(左から2番目):私は前職でAWSではない、別のクラウドを触っていて、クラウド自体には慣れていました。4月の中途入社前からこの研修を受講することは決まっていて、AWSは初めてでした。AWSの知識を身につけるとともに、マネジメントもやってみたいと考えていました。
-
実際に研修を受けてみてどうでしたか。
-
 櫻井:私はすでにAWSの開発経験があったので、マネジメント寄りのことを学べたのは良かったです。課題も抽出できました。それに加えて、これまで扱ったことがないツールも使ったので、勉強になりました。そうした経験をふまえ、今回のバーチャルOJTは私にとって思う存分試行錯誤ができる良い機会になりました。
櫻井:私はすでにAWSの開発経験があったので、マネジメント寄りのことを学べたのは良かったです。課題も抽出できました。それに加えて、これまで扱ったことがないツールも使ったので、勉強になりました。そうした経験をふまえ、今回のバーチャルOJTは私にとって思う存分試行錯誤ができる良い機会になりました。五十嵐:私はこれまで上流工程にあまり関わったことがありませんでした。しかし今回の研修で、クラウドはチームでヒアリングから要件定義、設計、構築まで初めて経験しました。クラウドならではのやり方に、次の工程のことを先回りして考える意識が身についていると思います。
 黒馬:システムの全体像を捉えて最適に設計をすることがとても難しかったです。また納期設定も2ヶ月と、とてもタイトな研修でした。しかしフォローが手厚くなんとか乗り切れました。全員が技術を一定水準分かっている上で、分担し協力することで、一気にシステムができあがっていくのを体験し、感動を覚えました。チームの一体感を抱きましたし、研修での感覚が今の仕事に活きているように思います。
黒馬:システムの全体像を捉えて最適に設計をすることがとても難しかったです。また納期設定も2ヶ月と、とてもタイトな研修でした。しかしフォローが手厚くなんとか乗り切れました。全員が技術を一定水準分かっている上で、分担し協力することで、一気にシステムができあがっていくのを体験し、感動を覚えました。チームの一体感を抱きましたし、研修での感覚が今の仕事に活きているように思います。後藤:私はクラウドを触ったことはありましたが、お客様のヒアリングをしたことがなく、その部分がとても難しかったです。失敗してもフォローの体制があり、整った環境の中で普段経験できない業務を体験でき、良い勉強になりました。
-
今後実際の業務で活かしていきたい点を教えてください。
-
黒馬:最近の新しい案件は基盤がAWSの場合が多いのですぐに活用できそうです。また、後からプロジェクトに参画した場合でも、キャッチアップが楽になりそうです。
加えてクラウドは変化のスピードが速いので、技術習得も継続して求められます。今回のように調べながらプロジェクトの業務に落とし込むやり方は良い経験になりました。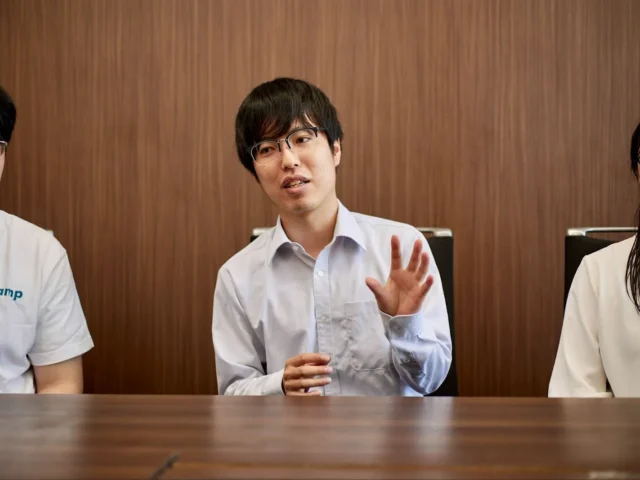 後藤:業務上、すぐに顧客ヒアリング、開発要件などに携わる機会は少ないように思います。ですが、クラウドで学んだものの見方やプロジェクトの進め方は社内の業務改善やシステム改善に活かせるように思います。
後藤:業務上、すぐに顧客ヒアリング、開発要件などに携わる機会は少ないように思います。ですが、クラウドで学んだものの見方やプロジェクトの進め方は社内の業務改善やシステム改善に活かせるように思います。五十嵐:受講後、今回の研修の参加をきっかけとして、クラウドの案件に携わることが増えています。バーチャルOJTの決められた期間内で、平行してタスクを進めてシステムを作り上げていくことを学び、プロジェクトが短納期の案件にも活かしていけると思います。
今後の人材育成計画、スカイアーチネットワークスへの期待について
-
実際に研修を受講したメンバーからは概ねポジティブな感想がありましたが、今後の研修活用についてはいかがでしょうか。
- 右田:当社はコアビジネスが印刷とデジタルソリューションで、他社ではなかなかないユニークな組み合わせです。このユニークネスをさらに尖らせるため、クラウドを活用し、印刷+デジタルソリューションの可能性をさらに伸ばしていきたいと思います。
大串:現在、当社だけでなく、トッパングループ全社的にクラウド教育を推進しています。冒頭に申し上げた資格取得がその一つです。しかし従来のクラウド教育だけで終わってしまうと、今回の研修のテーマである「実務で使える」はかないません。今後は実務で使うために、どういった内容の教育機会を創出すべきか引き続き検討が必要だと考えています。
ぜひ研修だけでなく、クラウド実装に向けて、全体的な進め方を一緒に進めていきたいと思います。田坂:今回の研修を経て、クラウドを使いこなすに至るまでの課題が抽出できたことは大きな成果の一つに挙げられます。また、積極的に研修を受講し、受講する前よりも少しでも自信を持ってもらえたのも喜ばしい成果です。
受講したメンバーを中心に、今回抽出できた課題や、得た学びを持って当社の中でクラウドの裾野を広げていってほしいと思います。
株式会社スバルITクリエーションズ(以下、SIC)は、SUBARUグループで唯一のIT専門企業です。グループのIT基盤を支える企業として、日々システム開発・保守・運用を行っています。SICが支える業務分野は製品の企画・設計からマーケティングなど多岐にわたります。
今回の導入事例に至るには、SICの技術的成長を追求する思いがありました。IT技術の進歩、DX推進や社員のリスキリングといった世の中のトレンドがある中で、自社とグループにとって求められる技術を見極め、必要なスキル選定とプロジェクトを構想した築地常務取締役、人事制度設計とプロジェクトの計画を企画した里岡氏に経緯と狙いを、実際にAWSの研修を受けた宮本さんに感想をそれぞれ伺いました。
導入ポイント
- AWSに特化した、高い専門性があると感じた
- 変化スピードの速いクラウド業界なので、専門家のナレッジを活用したかった
- お任せできる実績があり、安心感があった
事業概要
-
SICの提供するサービスについて教えてください。
- 築地:SICはSUBARUの、グループ唯一のIT子会社です。外販はしておらず、親会社の業務を受託して開発・運営をしています。
導入経緯、導入前の課題
-
今回AWSの研修サービスを受けていただきましたが、そもそもどういった経緯で研修サービスの発注に思い至ったのでしょうか。
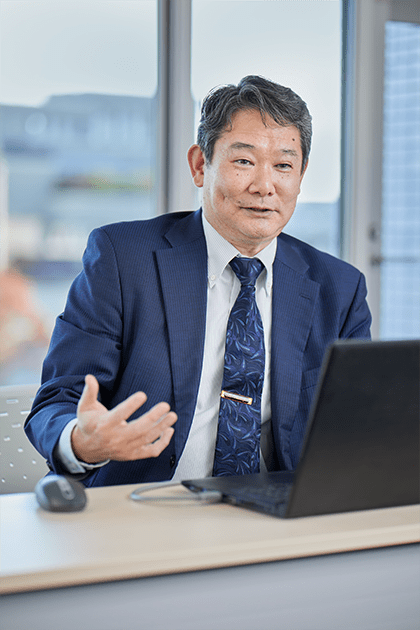 築地:経緯をお話するには少し話を遡ってお話する必要があります。
築地:経緯をお話するには少し話を遡ってお話する必要があります。
私たちの親会社SUBARUはメーカーですが、SICはIT企業です。グループといえども業務が異なるため、以前の人事制度はIT企業としては少し合わない部分もあり、数年前に里岡が主導して人事制度の改訂を行いました。その際に資格取得補助制度なども新設し、エンジニアによりフィットする人材ガイドラインを作っていました。
その頃から段々と世の中でもDX、IT人材不足が叫ばれるようになりました。最近ではリスキリングもトレンドですよね。特にIT人材不足は私たちも痛感していたので、数年前に作った人材育成ガイドラインに+αの教育が必要だと考えたのが、今回の研修を受ける大きな背景としてありました。
ちょうどタイミングを同じくして、2024年にSICは、株式会社SUBARUに吸収合併が決まりました。今後はより一層、グループ全体のIT技術の中核を担うことを求められるでしょう。その準備もかねて、習得したいスキルをいくつか特定し、新たな育成計画を策定しました。その中の一つがクラウド領域で、AWSだったのです。
-
育成計画の見直しをされていたということですが、現状ではどのような課題感をお持ちだったのでしょうか。
 里岡:以前私が主導して作った人事制度はITSS(※)をベースとしたスキルセットを想定し、設計していました。しかしITSSはベーシックな知識と知識実装をモデルとしています。クラウドやAIなど新技術が活用されている今、従来のモデルでは組織設計もカバーしきれないと限界を感じていました。
里岡:以前私が主導して作った人事制度はITSS(※)をベースとしたスキルセットを想定し、設計していました。しかしITSSはベーシックな知識と知識実装をモデルとしています。クラウドやAIなど新技術が活用されている今、従来のモデルでは組織設計もカバーしきれないと限界を感じていました。
※参考 ITスキル標準/ITSSについて、https://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/
-
具体的にどのような育成計画を立てられていたのでしょうか。
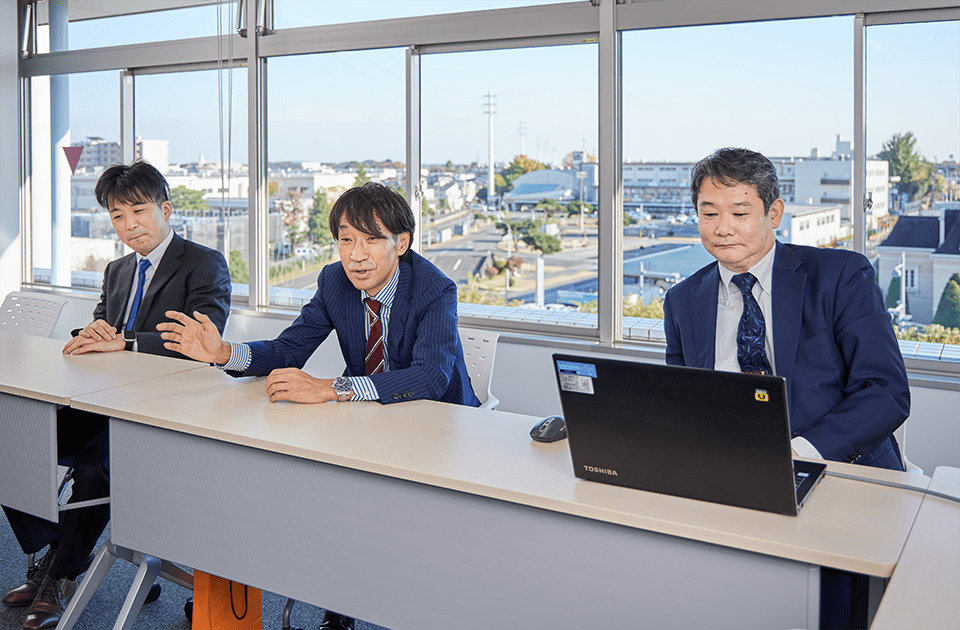 築地:新たな育成計画を立て、求められるスキルセットを設計をし、人事制度に紐づけるところまで進めてはみたのですが・・・やはり高度IT人材を輩出するハードルの高さを改めて感じました。短期的には良くても、中長期的に機能しなければなりません。すでにスキルのある社員を育てても後が続かなければ人材不足の課題はそのままです。そのため、途中で軌道修正をし、まずジュニア~中堅層の社員に対する教育から着手することにしました。
築地:新たな育成計画を立て、求められるスキルセットを設計をし、人事制度に紐づけるところまで進めてはみたのですが・・・やはり高度IT人材を輩出するハードルの高さを改めて感じました。短期的には良くても、中長期的に機能しなければなりません。すでにスキルのある社員を育てても後が続かなければ人材不足の課題はそのままです。そのため、途中で軌道修正をし、まずジュニア~中堅層の社員に対する教育から着手することにしました。
里岡:変化スピードが速く定義づけさえ難しい新技術系も、新たな育成計画のスキルセットの中に盛り込まれました。しかしそれらを自社内だけで習得していくのが難しいのは明白でした。そのため、新技術は分野に特化した企業、特に新技術を日々自分たちでも使いリアルを知っている企業から学びたいと考えていました。
AWSを選んだ理由
-
クラウド技術の中でもAWSを選んだ理由についてお聞かせください。
- 築地:オンプレミス環境での開発が基本ではありますが、グループの中でも一部ではクラウドが活用されています。マルチクラウドではありますが、調べてみた中では、企業向け研修サービスが比較的多く存在していたのがAWSということもあり、AWSから始めることとしました。
スカイアーチのAWSトレーニングを選んだ理由
-
スカイアーチのサービスをお選びいただいた理由ついて教えてください
- 築地:スカイアーチ社自身が同じAWSトレーニングを実践し、AWS有資格者を高い合格率で輩出している実績が最も大きな理由です。スカイアーチの人事担当者や営業担当の方も、実際にそのAWSトレーニングでAWS認定を受けたとお聞きして、とても驚き、自社でも成功できるイメージがわきました。また、スカイアーチがAWS公式認定トレーニングパートナーであることも安心感があります。
研修中の体験談
-
ここからは実際に研修を受け、SICでは最高得点で合格された宮本さんにお話を伺います。研修期間中は業務と並行して受講していただきましたが、どのように1日のスケジュールを組んで過ごされましたか。
- 宮本:研修期間中は午前中に業務、午後から研修というスケジュールでした。午前中に終わらなかった仕事は研修後に少しだけ対応して、残りは翌日に回すという感じでした。
業務に支障が出ないよう、受講者の中で期間をずらしながら日程が設定されていましたが、まさに私のチームの中に別の期間で受講するメンバーがいたので、仕事を分担しながら研修に取り組んでいました。日程が分かっていたのでお互い様ということで、助け合いながら業務を進めていました。研修はオンラインで研修会場との往復の移動時間がなかったので、時間を効率的に使えました。
-
SICでは様々な研修が用意されていると伺っています。今回の研修との違いは感じましたか?
 宮本:一般的な研修は一般論、概論を中心とした内容でした。しかし今回の研修はAWSに特化しており、ケーススタディが多く、ベストプラクティスがあるので、勉強しやすかったです。また、ハンズオンのパートもありました。そこではテキストの文章だけでは掴みきれないノウハウが出てきます。インプットばかりで受動的なスタイルの研修ではなく、アウトプット重視の研修でした。資格取得のための勉強ではなく、実践で使える知識が身につけられると思いました。受講してみて講師の方の「合格させる」熱意を感じました。
宮本:一般的な研修は一般論、概論を中心とした内容でした。しかし今回の研修はAWSに特化しており、ケーススタディが多く、ベストプラクティスがあるので、勉強しやすかったです。また、ハンズオンのパートもありました。そこではテキストの文章だけでは掴みきれないノウハウが出てきます。インプットばかりで受動的なスタイルの研修ではなく、アウトプット重視の研修でした。資格取得のための勉強ではなく、実践で使える知識が身につけられると思いました。受講してみて講師の方の「合格させる」熱意を感じました。
導入効果、今後ご期待いただくこと
-
研修への反応はいかがでしたか。
- 築地:当初の想定人数より、倍の申し込み数があって驚きました。
-
ちなみに宮本さんはどのような理由で申し込みされたのでしょうか。
- 宮本:グループ内でも一部でクラウド導入が進み、既存システムとの連携で、AWSに触れる機会が増えていました。そのような中で、基本的な知識を身につけ、スムーズな連携を図りたかったのです。
-
今後日々の業務で今回の知識を活用する機会はありそうでしょうか。また、そのような期待はありますか。
 宮本:今回受けた資格以外にも、関連する領域も勉強していって、幅を広げていきたいと思っています。有効期間が3年なので、資格をとればその分大変かもしれませんが(笑)。
宮本:今回受けた資格以外にも、関連する領域も勉強していって、幅を広げていきたいと思っています。有効期間が3年なので、資格をとればその分大変かもしれませんが(笑)。
里岡:来年度以降、プロジェクトが立ち上がった際に活躍してもらえるのを期待しています。





